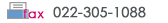東北大学災害科学国際研究所 今村文彦教授
根本宣彦アナウンサー 電話インタビュー
1月1日に発生した能登半島地震から1か月。津波被害や日本海側で発生する津波の特性、今後の備えについて東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授にインタビュー。今回の津波は日本海側が閉鎖空間だったことにより、大陸と日本列島で反射して何度も押し寄せる状況となり、津波注意報などが解除されるまで18時間かかった。また、海底活断層が海岸に近く、非常に早く能登半島沿岸に津波が到達した。このような即時津波から身を守るには、揺れが収まったら注意報警報を待たずに避難行動をとることが大切だという。また、半島ゆえに道路がふさがれてしまうと孤立してしまう地区があった。道路やライフラインを強靭化、自助共助の強化が必要となる。まだ大きな余震が発生する恐れがあるため、揺れと、雪や雨による土砂災害に注意ほしいとのこと。
———————————————————————————————–
石川県七尾市矢田郷地区まちづくり協議会会長 飯田伸一さん
藤沢智子アナウンサー、松尾武アナウンサー 電話インタビュー
七尾市最大の避難所の矢田郷地区コミュニティーセンター。発災後1か月は避難所、ボランティアスタッフの運営拠点となっている。地震発生後1時間半で開設し、700人以上が避難した。まちづくり協議会の会長・飯田伸一さんやコアスタッフが分担して運営している。現在の避難者数は170人ほど。感染症対策のために、土足厳禁にし、区画整理を行った。今後は日常の生活を提供できるように動きつつ、経済の復興、心のケアなど進めていきたいと語った。