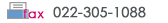南三陸町 平成の森球場改修終了 猪股猪一郎さん
伊藤晋平アナウンサーリポート
きのう、東北楽天ゴールデンイーグルスVS北海道日本ハムファイターズ戦(イースタンリーグ公式戦)の試合が行われた「南三陸町 平成の森球場」は、1991年に完成し、震災後「三陸地方の野球のメッカになるように」と町と応援職員が一体となって、3月に改修工事を終えて再オープンしました。
その中心人物、南三陸町の建設課の猪股猪一郎さん(71)は、球場の大規模改修が決定したのちに町の職員として採用されました。大手ゼネコン、岩手県の山田町の地元球場改修工事などに携わった後に、南三陸町の平成の森球場の復活に尽力しました。「甲子園球場」や「コボパーク宮城」と同じ種類の黒土と芝を使った球場にしたいと、水はけ低下などの悩みを改善しながら設計改修に励みました。
南三陸町の佐藤町長が「被災した町で辛抱強く頑張っている球児のために、甲子園の土を入れたい」と希望を伝えたことから、「コスト面」と「みんなの夢」を叶えるために、試行錯誤しながら作り出しました。土は鹿児島県から持ってきた黒土、岩手県の火山灰を混ぜた土を混ぜての混合土。バランスを見極めて土づくりを行いました。もちろん、その土の上にはコボパーク宮城と同様のきれいな緑の天然芝が敷き詰められています。
南三陸町の子供たちが、将来”この球場で野球をしたい”という夢をはぐくみながら、仲間とプレーする姿をみたい、と猪股さんは願っています。
気仙沼コヤマ菓子店 電話取材
藤沢智子アナウンサー
コヤマ菓子店は、「はまぐりもなかクッキー」で有名な気仙沼の菓子店です。「かわりない」とは言えどもここ数年は、小さな変化がたくさん見られました。仮設から本設へ商店を移す経営者や、新たに店を再建する事業主の方々が新しいお店の設計を始めたりと一歩一歩それぞれの状況を踏み出しています。コヤマ菓子店の小山裕隆さんも新しいお店の再建に、なんと浜松まで出かけて新店舗の設計を相談するということで新しい街づくり、お店作りをしようと前進しています。
以前から継続して行っている「気楽会」も35回を迎えました。気楽会の観光案内課ひとめぐりツアーは、〜初夏の内湾、美味しいカツオと共に〜というタイトルで6月11日に行われました。「何度でも通いたくなる旅」をテーマに行い今回は、観光まちあるきツアーで今が旬の鮮度抜群の美味しいカツオを食べました。
次回は、7月9日(日)9:00から、集合場所は気仙沼市民会館です。夏の気仙沼をみんなで先取りしませんか?もちろん地元に移住してきた皆さんもOK!参加費は2000円(昼食代別)です。とっておきの気仙沼をみんなで探して、その楽しみ方を伝授します。お問い合わせはkesennuma_kirakukai@yahoo.co.jp までお願いします。
※来週の「3.11みやぎホットライン」は、野球中継のためお休みです。