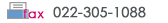亘理町吉田 斎藤美智子さん
佐々木淳吾アナウンサー 取材リポート
亘理町吉田に「お菓子のアトリエリモージュ」という小さなケーキ屋さんで、2003年開店当時から従業員として働いているのが、生まれも育ちも亘理町の斎藤美智子さんです。
津波で被災した斎藤さんは、住み慣れた故郷を離れて暮らす毎日にふと思う事があります。
震災当時、お父さんが「チリ地震では膝までしか津波は来なかった」という話を信じていたので、逃げませんでした。しかし、海から200mにあった平屋の自宅にはあっという間に波が押しよせのまれてしまい、波の中を浮いたり沈んだりして知らない方の家のカーポートに逃げ、その家で一晩を過ごしました。
2011年の4月からは4人の息子さんと、震災後に岩沼市内のアパートを借りて過ごすようになります。しかし亘理町の自宅のような近所づきあいではなく、上の階の人には結局会う事はなかったそうです。「これが都会の生活なんだ」と驚いた、と当時を振り返ります
その後、職場のお菓子屋へ戻り「再建」へと歩み始めます。地域の方々は親切でタオルがないと話すとタオルを下さったり、食器がないと相談すると食器を提供してくれたりと本当に親戚づきあいのような環境で、皆さんからの親切、あたたかさを更に震災後に感じるようになりました。そのおかげもあり3ヶ月後には元の場所で営業を再開することができました。
その後旦那さんの実家のある山元町に引っ越しますが、亘理町に比べて山元町には交流の場がたくさんありました。ご主人が山元町民だったという事もありここでも大変人に恵まれました。「何もなくても人がいれば大丈夫。故郷を離れたけれども、人と人とがコミュニケーションを取り合えればうまくいく」と感じたそうです。
今後も、顔を知っている人達が何かあった時に助けてくれる地元になるようにコミュニティづくりに取り組みたいと話してくれました。
ゆりあげさいかい市場 「栁屋」 栁沼宏昌さん
伊藤晋平アナウンサーリポート
栁沼さんは、ゆりあげさいかい市場の振興会会長を務めています。震災前は名取市沿岸南部の北釜地区で青果物の卸売り専門として勤めていらっしゃいましたが、今は八百屋がなかったさいかい市場で出店しています。震災後、市場は間もなく5年を迎えますがまだまだたくさんのサポートをしてもらっているな、と感じるそうです。
さて、栁屋を5年前に開業した栁沼さんですが今後の本節移転に向けて、店の営業形態をどうするか悩んでいます。本設に移転する時こそ「0」に戻れるからこそ、タイミングや店の軸(コンセプト)について真剣に考えなければ、と思っているそうです。
近々、本設商店街が出来る予定ですが、スピード重視で利用者を置き去りにしている感じが拭えないと思っています。そこで本当に商売が成り立つのか、もっと意見を反映してくれないかなど自問自答が続きます。
悩ましい問題がすべて解決すれば、すぐに飛び込みたいとの思いがありますが自分の新しいお店の将来を考えると、何事にも慎重にしていかなければ、と思いを巡らせます。