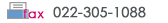・岩沼の農業で復興を 岩沼市 八巻文彦さん
取材リポート 飯野雅人アナウンサー
岩沼市で農業を営む八巻さんは、千年希望が丘の3号基のに元々あった農地を復旧させる「災害農地復旧事業」を手掛けています。相野釜地区には、かつて震災前にメロンや株などが栽培されていました。
東京ドーム2個分の広大な農地では、とうもろこしやサツマイモを栽培しています。去年から八巻さんは岩沼復興アグリツーリズムを開催し、ただ植えるだけ、ただ収穫するだけでなく“育樹”(定植から収穫までを管理)をし、岩沼へ足を運んでもらう機会をもちたいと、モニターツアーも実施しています。震災でいろいろなものを失い、色々なことを学んだと話す八巻さんは、「育樹を通じて岩沼市を学びの場に変え、震災を風化させず、ここから情報を発信し続けたい」と心の原動力をについてお話し下さいました。
○「千年希望の丘」岩沼復興アグリツーリズムhttp://minnanoie-iwanuma-infocom.com/agritourism/
・七ヶ浜町カフェレストランSEASAW 5/3 OPEN
代表 久保田靖朗さん
取材リポート 伊藤晋平アナウンサー
5/3に、七ヶ浜町菖蒲田浜に新たなカフェレストランSEASAWをオープンさせた久保田靖朗さんは、震災後七ヶ浜町に移り住みました。菖蒲田浜の魅力に吸い寄せられ、震災で一度は失いかけた浜を大事に思い、そして元の浜に戻していく第一歩として、地域の住民の皆さんとワークショップを行いながら地域に根付いたカフェをオープンさせました。食材も地元の漁師さんや農家さんと連携して、シュンな物を旬な食材として提供します。
菖蒲田浜にお店の灯りをともし、みんなの気持ちをほっとさせるような場所づくりをこれからも手掛けます。菖蒲田浜では今年、海開きができる環境が整いました。仙台から一番近い美しいビーチにもう一度賑わいを戻す第一歩が、今、踏み出されました。